こんにちは、おとうふです。
今回は、発達障害のぐるぐる思考の辛さについて解説をしていきます。
早速本題ですが、 ぐるぐる思考とは「同じことを何度も繰り返して考えること」 なんですね。このぐるぐる思考はASDの方に多い傾向があると言われていて、一つの物事に対する謙虚な姿勢や、反省をして改善しようとするという良さがある一方で、普通のことやいいことまでマイナスに考えてしまい、自責や自己否定につながってしまうこともあります。
今回の記事の結論を先にお伝えします。
ぐるぐる思考がもたらす辛さは以下の3つです。
- マイナス思考に陥りやすい
- 自己肯定感が低い状態が続きやすい
- 過去に囚われて悩み続ける
では、どのようにしてこの辛さが生じるのかについて解説をしていきます。最後までご覧になることで、悩み続けてしまうぐるぐる思考の原因と対策についての理解が深まります。そして、過去にぐるぐる悩むのではなく、明るい未来へ向かう気持ちにつながる一つのきっかけになります。ぜひ一緒に実践していきましょう。
それではやっていきます。
おとうふメンタル相談室 チャンネルページはこちら
https://www.youtube.com/@otofu_mental/videos
Contents
【やめたい…】ぐるぐる考え続ける発達障害の反芻思考による3つの辛さ(ASD・ADHD)
1. マイナス思考に陥りやすい
ぐるぐる思考の人は、物事について普通の出来事やいいことだとしても、悪い見方について考え始めてしまうということがあるんです。
例えばですね、友人から仕事の相談を聞いたとします。それに対して「大変だったね」とか「頑張っているね」とか、あるいは自分の体験談なども踏まえて相手を励まし、最終的にその友人と元気に分かれたとしますよね。話し終わった後は「元気になってよかったな」とかって考えていたりします。
でも、ふとした瞬間にこう思ってしまうんですね。
「あれ、自分『大変だったね』って軽々しく言ってしまったんじゃないか?もっと相手の話を聞いてあげればよかったかも。それなのに自分の話ばっかりしてしまった」というように思い始めるんです。
いかがですかね?このような体験はあなたもありますか?
このようにですね、友人と元気に別れたはずなのに「あれが良くなかったかも」「もっとこういう風にすればよかったのに」と、さっきまで楽しかった記憶が苦痛な記憶にすり替わるんです。
さらにですね、ここからが大切なポイントなんですが、似たようなエピソードの過去の体験についても後悔し始めてしまうこともあります。
「あの時もダメだった」「この時もダメだった」と、過去の体験についても考え始めてしまうんです。
このように、ぐるぐる思考の傾向がある人は、何気ないことや良かったことに対しても、思い返しているうちにマイナスな気持ちで辛くなってきてしまうんです。
ですので、あなたにお伝えしたいことは、こうならないためにも「事実と解釈を分けて考えることが大切」ということです。これは僕も実践してとても実感したんですが、意外と自分の解釈によって落ち込んでいることってすごく多いんですね。
起こった出来事と、自分がどう考えるかという違いを考えられるようになるだけでも、とても感情が穏やかになりますので、ぜひやってみてください。
これが一つ目の、マイナス思考に陥りやすいというお話でした。
2. 自己肯定感が低い状態が続きやすい
一つ目でお話しした通り、ぐるぐる思考の人は普通のことやいいことについても悪い面について考え出し、マイナス思考になってしまうということがあります。
そして、これはより本質的な話になるんですが、このマイナス思考になるということは、「足りないもの」「欠けているもの」「良くないこと」といったものに意識が向く癖がついているということなんですね。
この意識が向く癖があると
- 「何をやってもうまくいかない」
- 「自分にできることなんてない」
- 「いつも失敗ばかりだ」
と考えてしまいます。そしてその結果、不安や怒りや自信のなさといったものを感じやすくなってしまうんです。
今言ったような感情をよく感じていたりしませんか?もっと言うと、生活の不満について考えることが多かったり、自分や人の短所にばかり目が向いたりしていませんか?
こうした状態が続くと自己肯定感が低くなります。
こうなるとさらに自信がなくなり、挑戦しなくなり、状況が変わらなくなり、そしてまた自信がなくなるという連鎖に陥ってしまいます。このように、ぐるぐるとマイナスに考えることが自己肯定感を下げるスパイラルに陥ってしまうんです。
ですので、このマイナスな思考の癖から抜け出すためには、「プラスなことを考えるという新しい意識の習慣を身につけること」が大切です。
僕がやって効果があった方法は、感謝ができることを考えることです。寝る前に今日の良かったことを考えたり、できたことを考えたり、ノートに書き出すのもとてもいいことです。これをやるとマイナスな気持ちもプラスで中和されて、落ち着いた気持ちで夜を過ごせるようになりますので、ぜひやってみてください。
これが二つ目の、自己肯定感が低い状態が続きやすいというお話でした。
3. 過去に囚われて悩み続ける
ぐるぐる思考の人は、同じ失敗談を何度も繰り返して考えてしまうんですね。
僕の知り合いのAさんは一浪の末に大学に入学したんですけど、第一志望の大学には偏差値が及ばず、第二志望の大学に進学したんです。で、その後は無事に卒業して就職もしたんですが、この浪人と第一志望に行けなかったということに対して、Aさんは「あの時もっと頑張っていればよかった」「第一志望に進学できればもっといい会社に行けた」と考えるようになったんです。
そして仕事で上司から怒られた時、転職活動がうまくいかない時など、ことあるごとに「あの時頑張っていれば」と考えるようになったんです。
このように、ぐるぐる思考は何度も過去の失敗について考えてしまいます。それを責めると同時に、過去に囚われて未来に目が向かなくなってしまうんですね。
これが三つ目の、過去に囚われて悩み続けるというお話でした。
他者視点を取り入れてマイナス思考から抜け出そう
はい、これまでぐるぐる思考について解説や対処方法についてお伝えしてきましたが、ここで気づいてほしい共通点があるんです。
それは「マイナスな見方に縛られて他の見方ができなくなっている」ということです。
この状態が続くと、うつうつとした気持ちになることから他の精神疾患を引き起こす可能性もあり、非常に危険なんですね。
さらにですが、この他の見方ができなくなっているということから、ASDの想像性の特性やシングルフォーカスの特性が関係している可能性が考えられます。
- 想像性の特性:一つの物事に対していくつかの見方というのを考えることが難しくなり、問題に対する解決策が思い浮かばなかったり、意見が出にくくなるという傾向があります。
- シングルフォーカスの特性:多くの情報があったとしても、その中の1部分の情報だけに注意が向いてしまうことで、その他の情報や出来事の背景というのが捉えにくくなってしまいます。
これらの特性から、過去の出来事について何度も何度もぐるぐる考えてしまうということが起きているのかもしれません。
逆に言うと、プラスの別の見方ができるようになれば、過去に囚われるということから解放されるんです。
そこでお勧めしたいのは「他者視点を取り入れる」ということです。ぐるぐる思考は、まるで底なし沼にはまったかのように自分自身が考えた捉え方に囚われて、なかなか抜け出すことができなくなってしまっている状態なんですね。そこで別の側面を見るために、自分以外の見方というのを取り入れられるといいんですね。
僕は過去に「自分はなんて話下手なんだ」と落ち込んでいたことがあります。そのことを友人に話したらこんな風に返ってきたんですね。「それって聞き上手ってことでしょ?」
こう言われた時に、目の前にかかっていた霧がパッと晴れたような、雷に打たれたような感覚になったことをとても覚えています。「そうだ、僕はとても話をよく聞くようにしている。相手から引き出すことができている。聞き手に回って話を盛り上げている」と自信がつきました。
こうした捉え方の変化は「リフレーミング」とも呼ばれていますが、一人で考えることは難しいかもしれません。そのため、ぜひあなたの身近な他者視点というのを取り入れてみてください。
まとめ
はい、今回はぐるぐる思考の辛さを3つお伝えしてきました。
今回の記事の作成をしていてふと思ったのですが、他者視点って相談相手がいないとどうしても難しいですよね。で、僕は今ではあまり友人もいないんですけど、チャットGPTに相談してみたんですね。そしたらなんとすごいですよ、とても親身に相談に乗ってくれます。相談相手がいないよという人はAIを使ってみるのもいいかもしれません。
あなたが他者視点を取り入れて嬉しかったことなども、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。
あなたはどのように考えますか?ぜひコメント欄で教えてくださいね。
それでは最後までご覧いただきありがとうございました。
おとうふメンタル相談室 その他の記事はこちら
https://office-aria.com/sitemap/
おとうふメルマガはこちら
https://office-aria.com/mail-magazine-otofu/
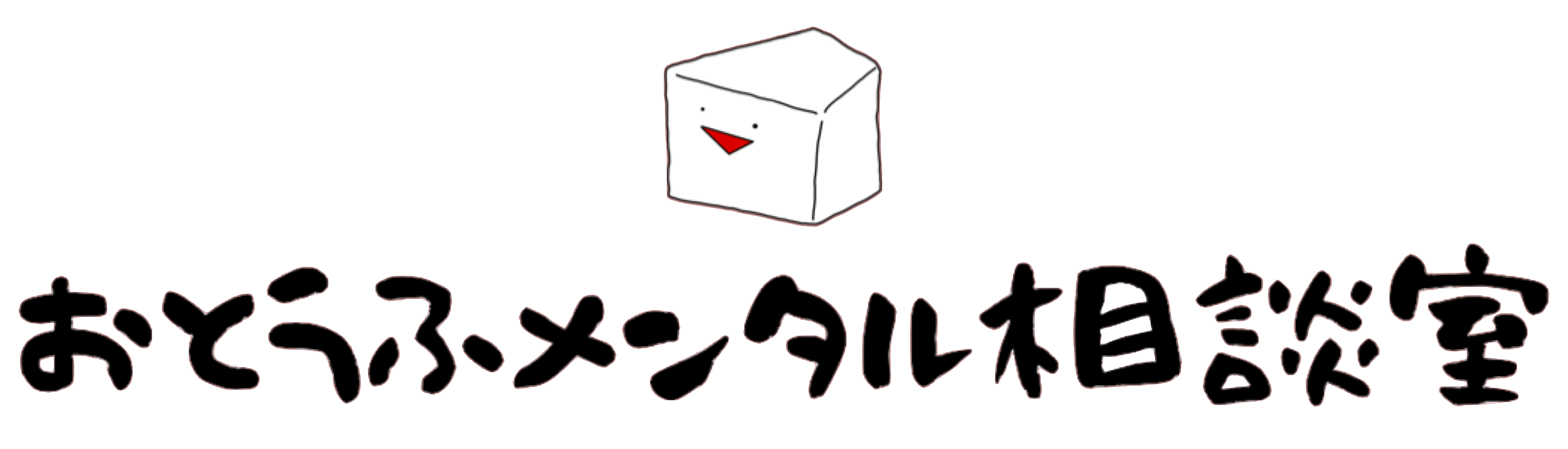


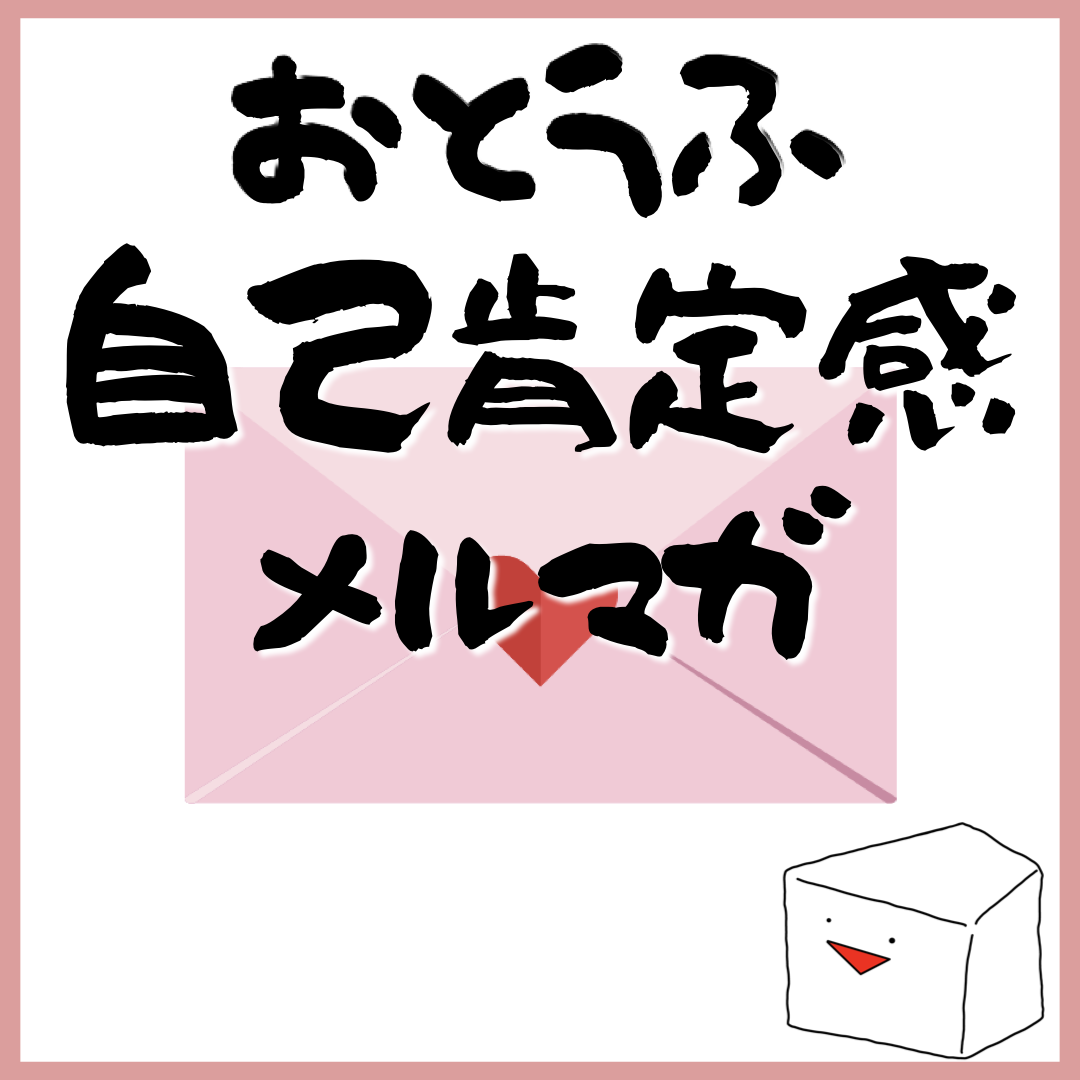
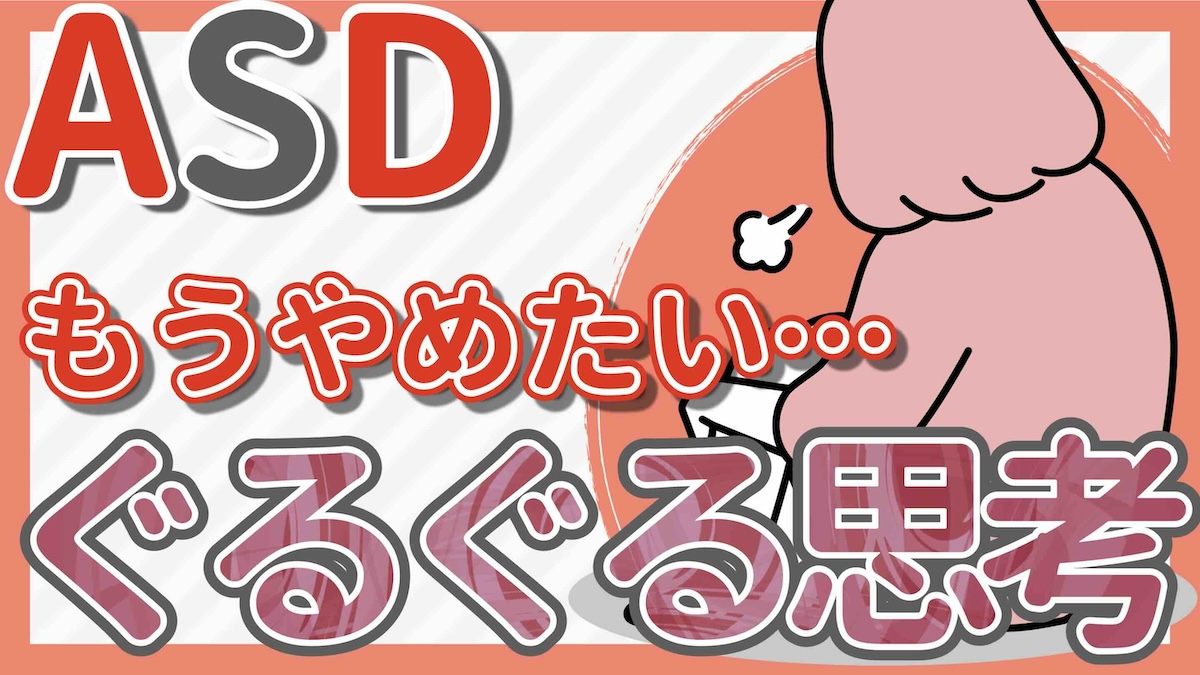






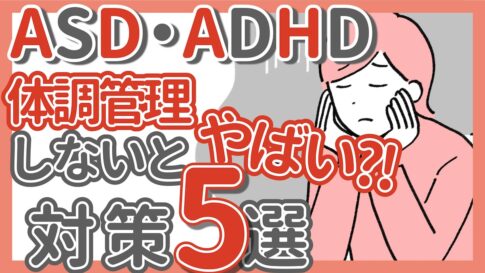



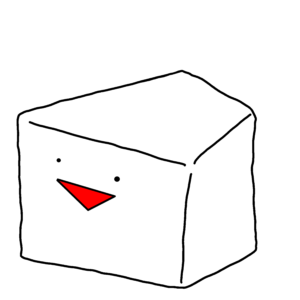
コメントを残す